転勤先を重ねるハザードマップで調べると、最大5mの内水氾濫・洪水の水害リスクがわかりました。
できれば災害リスクがハザードマップに無い場所を生活圏にしたいのですが、そうもいかない事情がある方もいらっしゃると思います。
私の場合、職場、病院、学校、買い物、駅等が全て徒歩数分圏内の便利な家にどうしても住みたい。
しかし、最大5mの内水氾濫リスクがある。
地域の広範囲が当該リスク地域であったため、最寄りの対応避難所が車で20分。
その避難所付近に住めば災害リスクはグッと下がりますが、日頃の生活が不便になります。
利便性と、防災の折り合いをどうつけるか。
私の場合、最大5mの氾濫は許容することにしました。
ただ、「想定最大の災害がこないように神様に祈る」だけでは心許ないです。
そこで、以下の方針を家族で決めました。
- 自治体の出す警戒レベル3「高齢者等避難」時点で避難する
- できれば3階、少なくとも2階以上に住む
- 家財は火災保険で対応する
あくまで、防災の専門家でもなんでもないただの人である私が、私のために、家族と共に相談して決めた結論です。
考え方を共有させていただくとともに、何か参考になりましたら幸いです。
重ねるハザードマップが便利
国土地理院が提供している、地図から災害リスクを調べるサイトです。
特徴としては、
- 全ての災害リスクが1発で見える
- 【リスク検索】ボタンで想定災害リスク解説
「重ねるハザードマップ」と検索してみてください。
すべての災害リスクが1発で見える
各自治体が公表しているハザードマップは、「災害の種類ごと」にマップが作られています。
例えば、水害ハザードマップなど。
重ねるハザードマップを見つけるまで私は、自治体のホームページから、すべての地図をダウンロードして、1個1個調べていました。
各ハザードマップを重ねて同時に表示できる。
そんな夢のようなサイトが、重ねるハザードマップです。
【リスク検索】ボタンで想定災害リスク解説
また、ど素人の私は、こんな疑問が湧きました。
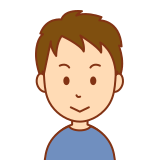
重ねるハザードマップで、自宅付近に色がついた。
色がついたということは、なんらかの災害リスクがある。
でも、具体的にどんなリスクがあるのよ。
これを解説してくれるのが、【リスク検索】ボタンです。
地図の右上くらいにある、こんなボタンです。↓

ここを押してから、解説して欲しいエリアをクリックすると、その地域の災害リスクを解説してくれます。
例えば、3mの浸水リスクがある地域の例で言うと…
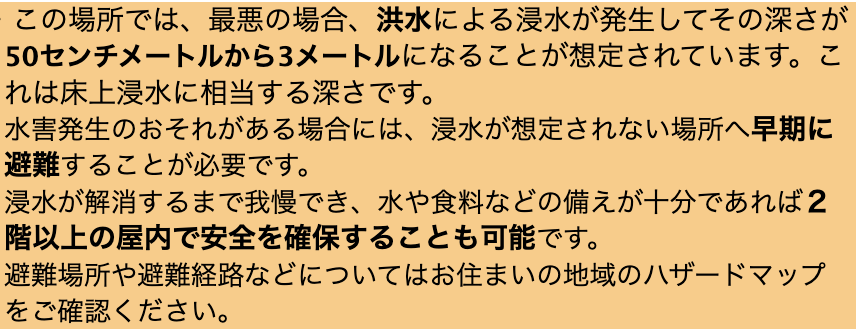
こんな感じで、リスク解説をしてくれます。
浸水レベルと建物の階数目安
水害ハザードマップ作成の手引き(平成28年4月)に基づいて浸水ランクの配色を行っています。浸水深等の閾値は、一般的な家屋の2階が水没する5m、2階床下に相当する3m、1階床高に相当する0.5mに加え、これを上回る浸水深・津波基準水位を表現するため、10m、20mを用いています。
国土交通省「浸水ナビ」のよくある質問7番目への回答より引用
- 0.5m:1階の床が浸水する
- 3m:1階が沈んで2階の床下あたりまで浸水する
- 5m:2階が沈む
こういうことらしいです。
警戒レベルについて
国土交通省「気象庁」のホームページ該当ページを読んだ上での私フィルターを通した理解としては
- レベル1:大雨とか、災害発生するかも
- レベル2:注意報。まだ焦らず避難などの確認しとこう
- レベル3:避難に手間取る人(高齢者、障害者、乳幼児など)は逃げ始めて
- レベル4:避難所開設してるから、なるべく逃げて
- レベル5:もう動くと逆に危ないからその場で身を守って
こんな理解です。
逃げるなら3~4。
5になるともう動くと逆に危ないので、たとえば自宅の中で一番高いところに垂直避難するなど、その場で命を守る行動を全力でとることが推奨されるようです。
避難所選び〜Yahoo!防災速報に登録〜
災害が発生したその瞬間、私は冷静になれません。
「こうなったら」「こうする」
と決めておいて、とにかくその通り愚直に動くことがせいぜいでしょう。
そうすると、事前準備が大切に思います。
Yahoo!防災速報アプリは、設定した各災害の状況に応じた通知設定、避難場所の登録、他、防災の知識などなどがたくさん詰め込まれております。
関連過去記事は以下です。
↓避難場所の登録方法について
↓他、ハザードマップやYahoo!防災速報の使い方について
我が家の方針再掲
- 自治体の出す警戒レベル3「高齢者等避難」時点で避難する
- できれば3階、少なくとも2階以上に住む
- 家財は火災保険で対応する
転居先は、最大5mの浸水リスクがあります。
ただし私は、日頃の生活(出勤、買い物、病院、学校、駅など)の利便性を優先しました。
が、リスクを放置して神様に祈るだけでは心許ないと感じました。
そこで、高齢者や障害者、乳幼児などのいらっしゃる、避難に時間がかかる「レベル3」時点で避難することとしました。
また、5mは建物でいうと2階が沈むのが目安です。
日頃、せめて2階以上に住むことで、不意打ちに備えます。
そして、実際に被害に遭った場合は、家財は一旦諦めて命を最優先します。
被害にあった家財は、火災保険で対応します。
そして、賃貸という強みを活かし、引っ越します。
こういう方法でリスクを許容することとしました。
関連記事
当ブログの防災関連記事は、こちらをクリックいただけますと一覧表示されます。
もしよろしければ、併せてご覧ください。
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
このブログが、あなたがあなたらしく生きるための土台づくりの、何かのヒントになりましたら幸いです。
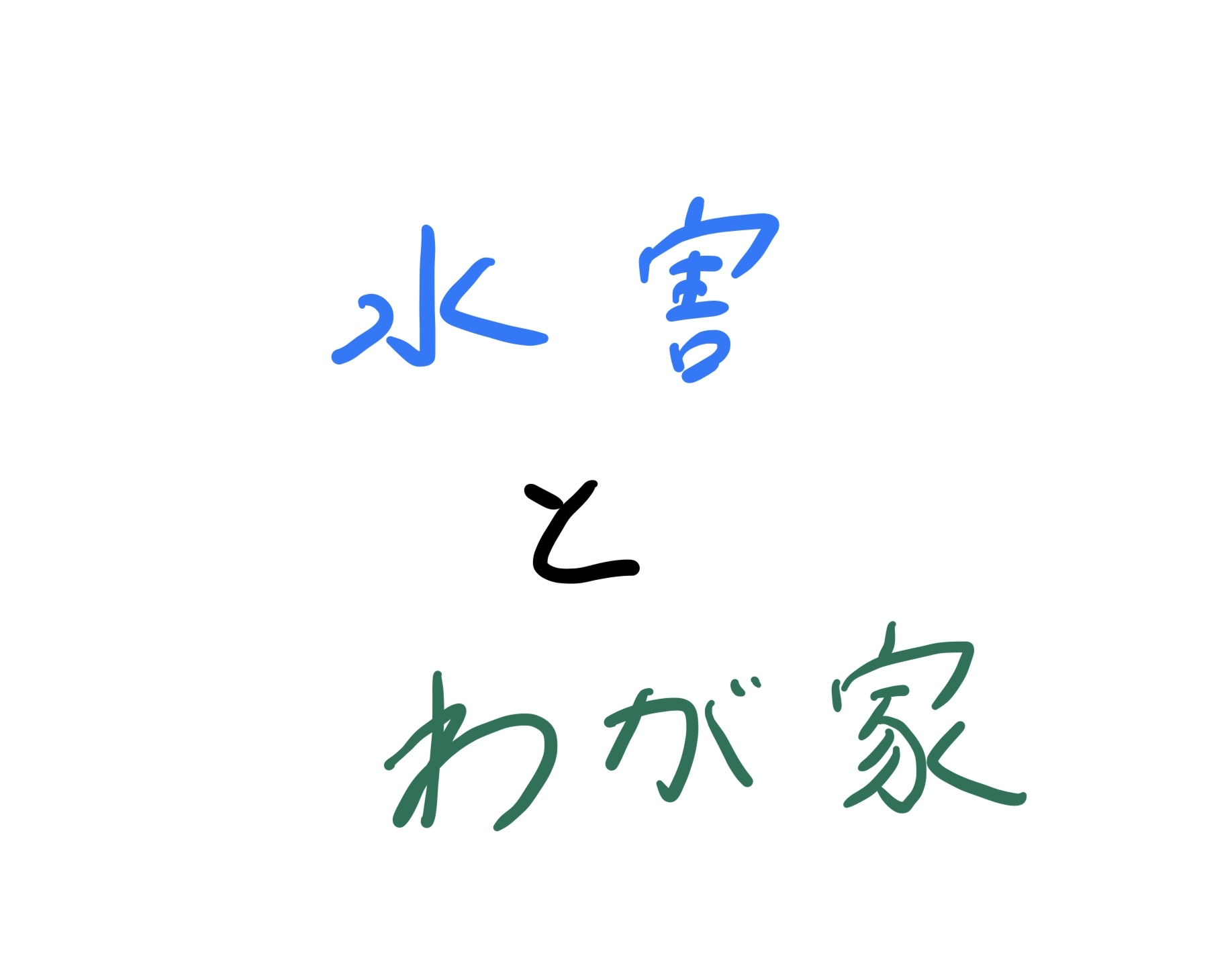

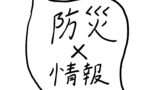


コメント